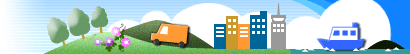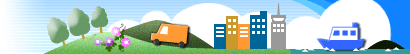さて、話はボブ・ディランである。
ライブでのボブ・ディランの歌声は、どんなバックバンドを揃えてもライブ終了まで一度もバックのサウンドとぴったり調和することはない。絶対に他と交わることのない規格外の歌声。いつでもどこでも、ボブ・ディランはバックとアンバランスなまま浮きあがってしまう・・・。私にとって、そのアンバランスこそ、クセになるボブ・ディラン、そのものなのだ。
ドキュメンタリー映画「ドント・ルック・バック」は、1965年当時のピリピリした若くてカッコいいボブ・ディランがぎっしり。私の知らない時代のボブ・ディランが、ついに国内盤DVDで体験できる。この映画は多くのアーチスト達に多大な影響を与え、その後の音楽シーンへの影響は計り知れないものがある。
プロモーション・ビデオのはしりといわれる「サブタレニアン・ホームシック・ブルース」の歌詞が大きく書かれたボードを歌に合わせてボブ・ディランがめくっていくオープニング・シーンは唯一演出された映像だ。
そして、聴衆の待つ暗闇のステージの中に、アコースティック・ギターとハーモニカだけを携えてひとり現れた彼が目に入った時、私は何だかたまらなかった。生ギターの弾き語りだけの演奏。フォーク・ソングから始まったボブ・ディランの長年に及ぶキャリアの太初のスタイル。何万人もの信者を生み、何千万もの人に訴えかけ、そして今や誰からも顧みられなくなった様式。しかし彼のかすれた例の歌声は、何ものにも馴染むのを拒んだ例の歌声は、これしかないようにギターとハーモニカにはゆっくりと溶け込んでいった。
全体としては、ステージそのものの映像がやや少ないようにも思うが、楽屋でのボブ・ディランの緊張感や、ある時は歌いたくない気分をもカメラは忠実にとらえている。
余談だが、映画の中のボブ・ディランは歌っている時以外、ずっとタバコを吸いっぱなしだ。私も昔タバコを吸っていたのでわかるが、相当なヘビースモーカーぶりに「おい、それで何本目だ!」と、思わずツッコミを入れたくなるほどだ。
デビー以来、アコースティック・ギターとハーモニカだけで、ひとり歌ってきたボブ・ディランは、その後突如としてエレクトリック・ギターをぶらさげステージに現れるようになる。サウンドもバックバンドを携えてロックン・ロール路線を突き進み、分厚いサウンドを好むようになっていく・・・。
当時の日本では、ボブ・ディランのアルバムがなかなか紹介されず、実際のリリースとのちぐはぐな印象に当時のファンはとまどい、いったいどう受け止めればいいのか、よく分からなかったらしい。
私は、リアルタイムでボブ・ディランを知らないが、サウンドが大きく変化しはじめたこの頃のボブ・ディランが一番好きだし、一番知りたいボブ・ディランでもあるのだ。
見慣れている街の風景がふとした拍子に違って見え、ハッとする瞬間がある。ボブ・ディランの作品から受ける印象はこれとよく似ている。目にしながら気づかずにいたものが突然立ち現れてきた驚きとでもいうか・・・。
「ドント・ルック・バック」の中でのボブ・ディランは、レンズの向こうから私たちの意識や感覚を大きく揺さぶり、現在の足元を見つめ直すよう促してくる。
でも、その映像をモニター越しに見ている私たちは、ただの現在でしかない。時間がオーバーラップして、なんとなく不思議な感じがする。しかし、1965年当時のボブ・ディランが、仮に現代に現れたとしても、思慮深く、時に主張し、時に幻想的な世界を描く様は、やはり異色でリアルな存在として映ることだろう。
だからこそレンズの向こうのボブ・ディランは、自信に満ちている。
フォーク・ミュージックからロックンロールへ、ビート・ジェネレーションから「ライブ・エイド」エイジまで、そしてプロテスト・ソングから宗教音楽や映画音楽まで、あらゆるものをくぐり抜けてきた彼は、しかし、その度ごとにボブ・ディランはボブ・ディランであるという神話性を高められ、本筋から外れた特別席へと追いやられてきた。デビュー以来変わることのない彼のあのひからびた例の歌声。それが年をとるにつれて円熟味を増し完成に近づくわけでもなく、またかつての勢いを失い次第に衰えていくわけでもないのは、彼があらゆる情緒を囲い込み、生きたまま伝説となったことを意味する。
ボブ・ディランの例の歌声を聴くたびに、私はいつしかそう思うようになった。
|